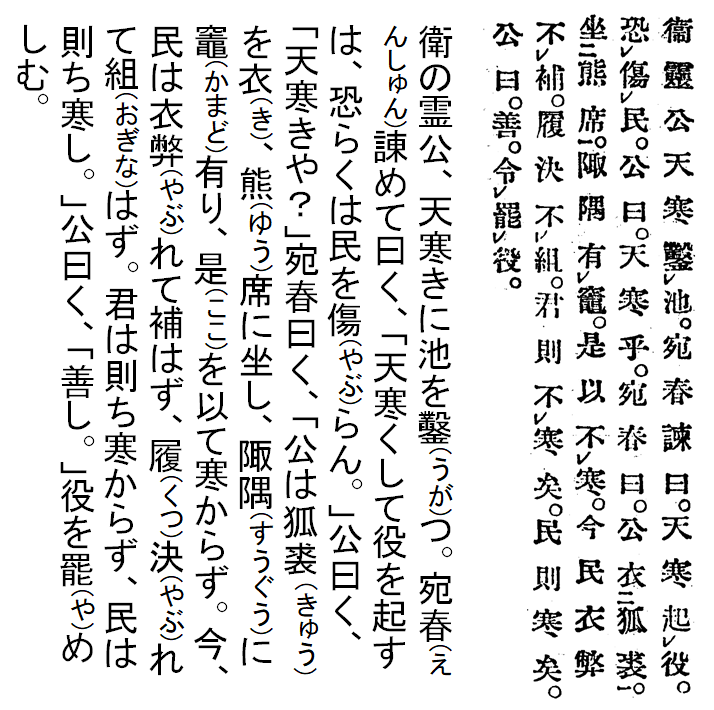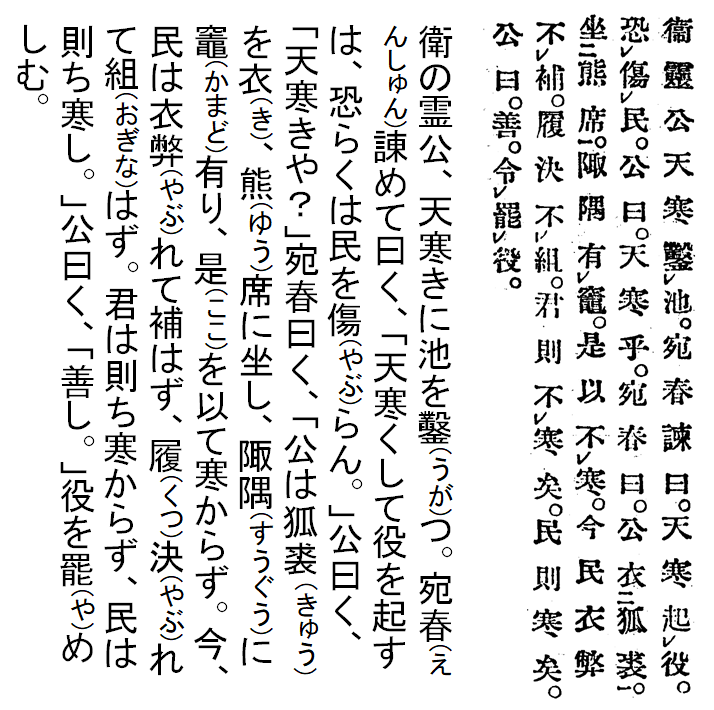第6課 述語で変わる文の性格②
──描写文〈形容詞述語文〉の構造「…が…だ」
| 王将軍老矣。 | | オウショウグン おゆ。 |
| 諸侯之宝三。 | | ショコウのたから サンあり。 |
| 姿容可愛。 | | シヨウ アイすべし。 |
| 戦略有利。 | | センリャク リあり。 |
| 回不愚。 | | カイは グならず。 |
形容詞または形容詞性の語句が述語になっている文を「描写文」という。主語が「どのようである」のか、その状態・性質などについて述べる文である。
◆6-1 形容詞が述語の場合
⓪王将軍老矣。
王将軍∥老〔矣〕。[オウショウグン おゆ](王将軍は年老いている。)
①其罪大。
其-罪∥大。[そのつみ ダイなり](その罪は大きい。)
②滅燕易。
〈滅燕〉∥易。[エンをほろぼすはやすし](燕を滅ぼすのはたやすい。)
③意気揚揚。
意気∥揚揚。[イキ ヨウヨウたり](意気が盛んだ。)
④夫子憮然。
夫子∥憮然。[フウシ ブゼンたり](先生はがっかりされた。)
⑤芙蓉香馥郁。
芙蓉-香∥馥郁。[フヨウのか フクイクたり](芙蓉の香りが盛んに匂う。)
形容詞には、単一の文字だけで構成されるものの他に、意味を担う文字に形容の言葉を作る接尾語「然」「如」「爾」などを付したもの、同じ文字を二つ重ねたもの(畳語)、連綿語などがある。右の例で言えば、③が畳語型、④が接尾語型、⑤が連綿語(畳韻型)に当る。
◆6-2 数詞が述語の場合
数詞は、述語になる場合は事物の量を表現することから、ある意味で記述の対象となる物の性質や状態を表すような言葉となるため、形容詞に類した性格を持つといえる。
⓪諸侯之宝三。
〈諸侯〔之〕-宝〉∥三。[ショコウのたから サンあり](諸侯の宝には三つある。)
⑥魯仲連辞譲者三。
〈魯仲連∥辞譲〔者〕〉∥三。[ロチュウレン ジジョウすること みたび](魯仲連は辞退すること三度であった(=三度辞退した)。)
⑦生還者十一。
〈生-還〔者〕〉∥〈十-一〉。[セイカンするもの ジュウにイチなり](生きて還る者は十分の一だった。)
※この場合の「十一」は「十分の一」の意で、割合を表わす表現。◀なお、分数に関しては次のような書き方もある。
⑧西域未服者百分之一耳。
〈西域-未-服〔者〕〉∥〈百分〔之〕-一〉〔耳〕。[セイイキのいまだフクせざるものは ヒャクブンのイチのみ](西域諸国の中でまだ服従しないのは百分の一に過ぎない。)
◆6-3 「可」を用いた句が述語の場合
〈助動詞「可」(…するのに値する)+情動を表わす動詞〉の組合せが、人にその情動を引き起こさせるような事物の性質を表す形容詞性の句となる場合がある。後世になると、一部の句は固定的に用いられて単語として形容詞化する。
⓪姿容可愛。
姿容∥〈可-愛〉。[シヨウ アイすべし](姿形がかわいらしい。)
⑨形貌可悪。
形貌∥〈可-悪〉。[ケイボウ にくむべし](顔貌がみにくい。)
⑩荒謬可笑。
荒謬∥〈可-笑〉。[コウビュウ わらうべし](でたらめさ加減がおかしい。)
「愛」という動詞は「かわいがる」という行為を表すが、「可愛」となると、ある事物が人に「かわいがりたい」気持ちを引き起こさせるような性質を持っている(つまり「かわいらしい」)ことを表す言葉となるのである。
◆6-4 動詞「有・無」「多・少」などを用いた句が述語の場合
〈存在動詞を用いた述語構造〉が事物の性質・状態などを評価する形容詞性の句となる場合がある。この場合の存在動詞の目的語には、ある価値や状態の意味合いを含むような名詞が入る。
⓪戦略有利。
戦略∥〈有+利〉。[センリャク リあり](戦略は有利である。)
⑪所言無理。
〈〔所〕言〉∥〈無+理〉。[いうところ リなし](言うことが無茶苦茶だ。)
⑫国家多難。
国家∥〈多+難〉。[コッカ ナン おおし](国家は多難である。)
◆6-5 副詞「難」などを用いた句が述語の場合
〈副詞「難」などを用いた句〉が事物の性質・状態などを説明する形容詞性の句となる場合がある。
⑬饑寒難堪。
饑寒∥〈難-堪〉。[キカン たえがたし](寒さと飢えが耐えがたい。)
⑭其鋒難当。
〈其-鋒〉∥〈難-当〉。[そのホウ あたりがたし](その鋭い矛先には立ち向かいにくい。)
◆6-6 主述構造を持つ句が述語の場合
〈主述構造の句〉が述語となる場合があるが、この場合は人物・事物の性質や様態を説明する表現となるため、形容詞性の述語と見なすことができる。このような場合の主述句の中に用いられる述語は主に形容詞か数詞である。
⑮平原君家貧。
平原君∥〈家∥貧〉。[ヘイゲンクン いえ まずし](平原君は家が貧しかった。)
⑯吾君徳薄。
〈吾-君〉∥〈徳∥薄〉。[わがクン トク うすし](わが君は徳が薄い。)
⑰吾年七十。
吾∥〈年∥七十〉。[われ とし シチジュウなり](私は年齢が七十である。)
◆6-7 否定の形
形容詞述語の否定は、述語の前に否定の副詞を加えて表わす。
⓪回不愚。
回∥不-愚。[カイは グならず](回は愚かではない。)
⑱名位不高。
名位∥不-高。[メイイ たかからず](名声や地位が高くない。)
◆6-8 比較対象をとる場合の構文
形容詞が述語になった文では「比較」を表現することができる。述語の形容詞に《「於」(または「于」「乎」)+比較対象》の前置詞構造を補語として加える形で表わす。なお、この場合、述語になるのは基本的には単一字からなる形容詞であり、句の形をとる形容詞性の語(「可愛」や「有利」など)は入らない。
⑲霜葉紅於二月花。
霜葉∥紅*《於+二月花》。[ソウヨウ ニガツのはなよりくれないなり](秋の紅葉は春の花より紅い。)
この形式の比較文において、比較する対象の間にどれだけ差があるかという数量の要素が加わる場合は、比較対象を示す「於」の前置詞句の後に数量補語を入れて表わす。
⑳六少於九三。
六∥少*《於+九》*三。[ロク キュウよりすくなきこと サン](六は九より 三少ない。)
●最上の表現
「莫」と前置詞句を用いた比較構文を組み合わせて「A莫○○於B」の形とすることで、「Aについては、Bより○○なものはない」、「Aについては、Bが一番○○だ」の意を表わすことができる。「莫」は、訓読では存在動詞「無」と同じように「なし」と読まれるが、文法的には英語の「nobody」または「nothing」に相当する、不存在を示す代詞の一種である。
㉑養心莫善於寡欲。
養心∥〈莫∥善*《於+寡欲》〉。[ヨウシン カヨクよりよきはなし](心を養うのには寡欲よりよいものはない。)
※なお、「莫」と反対の意味を表わす代詞は「或」で、英語の「someone」に相当する。「あるひと」と読まれる場合もあるが、やはり「あり」と存在動詞のように読まれる場合もある。形容詞述語文の例ではないが、補足として「莫」と「或」を用いた例文を挙げておこう。
㉒人莫救之。
人∥〈莫∥救+之〉。[ひと これをすくう なし](救ってくれる人はいない。)
㉓宋人或得玉。
宋人∥〈或∥得+玉〉。[ソウひと ギョクをうる あり](宋の人で玉を手に入れた者がいた。)
※㉒㉓の文はそれぞれ、「人無救之者。」「宋人有得玉者。」という存在文によってほぼ同じ意味を表わすことができる。(存在文については第8課で解説する。)
《読んでみよう》─『呂氏春秋』似順論より─
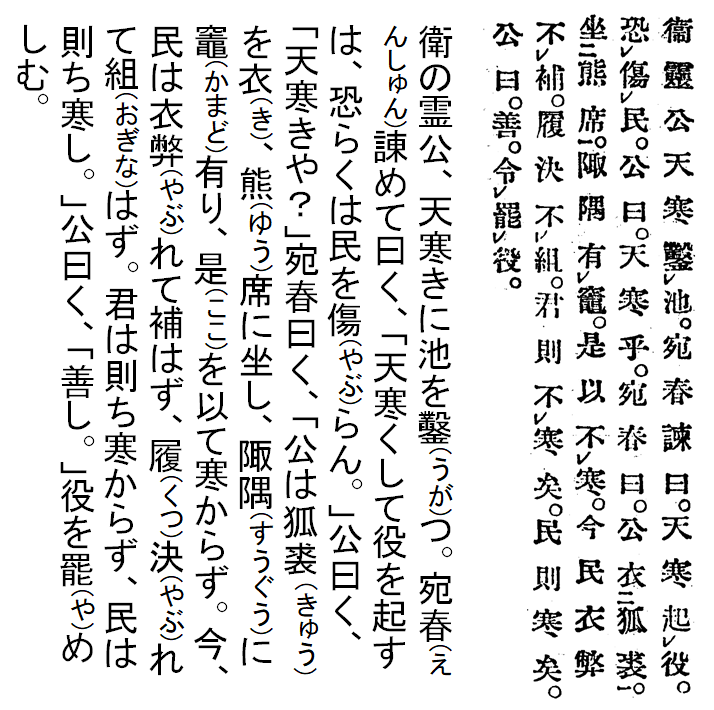
【注】
〔衛霊公〕春秋時代の衛国の君主。〔宛春〕魯国の人。霊公に仕える。〔陬隅〕かたすみ。〔衛霊公〕春秋時代の衛国の君主。〔宛春〕魯国の人。霊公に仕える。〔陬隅〕かたすみ。 〔組〕おぎなう。つくろう。「苴(しょ)」に同じ。